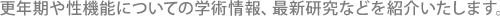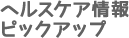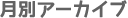-
早漏のエビデンスをベースにした定義:早漏の定義のためのISSM特別委員会の報告
2009年04月17日
【目的】
早漏(PE)の総合的なエビデンスをベースにした定義の作成
【方法】
PEの定義はいくつかある。最も一般的に引用されるのはAmerican Psychiatric Association’s Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – 4th Editionである。他の定義はエビデンス・ベースというよりオーソリティ・ベースであり、コントロールされた臨床試験や疫学的調査研究によるものではない。
このようなわけで、2007年8月ISSMは早漏の定義のためのISSM特別委員にPEに関する数人の専門家を定めた。
委員会は2007年10月にアムステルダムで会議を持ち、射精潜時、射精コントロール、性的満足度、および個人的/対人的苦痛に関するエビデンスを調査し、現在のPEの定義の長所と短所を評価し、新しいPEのエビデンスをベースにした定義の作成を行った。
【結果】
- 委員会は全会一致で、PEを定義する構成要素は早い射精、自分の能力である事の自覚、PEによるネガチブな体験・結果である事に同意した。
- 委員会はPEを次のように定義する事を提案した。男性の性機能障害であり、何時も腟内に挿入前あるいは挿入後約1分以内に射精、腟内挿入に関し射精を遅らせる事が出来ない、苦痛、悩み、フラストレーションあるいは性交の回避といったネガチブな体験・結果を特徴とする。
- この定義は腟内性交に関する長期的なPEを有する男性に限られたものである。
【結論】
このISSMの長期的PEの定義は最初のエビデンスをベースにした定義である。この定義は治療効果の診断および評価に関する新しい方法および患者報告のアウトカムの測定の開発を促進するであろう。そして、この疾患の真の発現率、新しい薬物および心理学的治療の効果に関する現在進行中の研究を勇気づけることになるであろう。
【原著】
McMahon CG,etal :BJU Int. 2008 Aug;102(3):338-50. Epub 2008 May 21.
An evidence-based definition of lifelong premature ejaculation: report of the International Society for Sexual Medicine Ad Hoc Committee for the Definition of Premature Ejaculation.
International Society for Sexual Medicine Ad Hoc Committee for Definition of Premature Ejaculation.
Australian Center for Sexual Health, Sydney, Australia【弊社コメント】
本報にもとづく早漏の定義は、”ISSM definiton of Primary Premature Ejaculation” として、ISSM(International Society for Sexual Medicine)で既に公表されています。
弊社HPの「早漏の定義(最新版)」も、本報を踏まえて更新致しました。EBMと呼ばれる、客観的根拠にもとづく医療の考え方が日米欧を中心とする現代医学の基本ですが、新たな治療法や新薬、医療器具を開発するには、たとえ経験的に知られている疾患であっても、疾患の定義そのものから客観的根拠にもとづいて決めないと、公的に認められません。
そして、エビデンス(客観的根拠)を求めるための膨大な調査に要する体制づくりや費用を全て国策にもとづき公的資金でまかなう事は困難で、多くの場合は、その疾患の治療薬や器具を開発する者の動機と接点を持つことになると思われます。
早
漏の定義につきましても、様々な変遷を経て、ようやくエビデンスにもとづく定義ができました。これは即ち早漏治療薬を開発するメーカーがスポンサーになっ
て検討が進められたものと想像できます。既に新たな早漏治療薬が欧米でリリースされている事実に関連づけられると考えます。(福)続きを読む
-
2009年04月10日
弊社製品取扱施設様 各位
平素より弊社製品にひとかたならぬご高配、お引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さて、ご高承の通り薬事法の販売制度改正にともない、2009年(平成21年)6月より、第1類および第2類OTC医薬品の小売販売の際に、文書による情報提供が販売者の義務となります(第2類は努力義務)。
つきましては、弊社推奨の説明文書案をご案内申し上げますので、貴店で弊社製品の説明文書を作成いただく際に、ご利用いただけましたら幸甚に存じます。
なお、本案は日本チェーンドラッグストア協会(JACDS)、日本OTC医薬品協会(JSMI)、日本セルフメディケーションデータベースセンター(JSMDBC)の合意案にもとづき、東京都家庭薬工業協同組合(東家協)のワーキンググループで合意された書式にもとづいて作成しております。下記リンク先のPDF形式ファイルをダウンロードのうえ、ご利用くださいませ。
(トノス・ハリーマークの説明にもご利用いただけます。)
続きを読む
-
2009年03月10日
2009年2月21日に第19回・日本性機能学会東部総会が長野市で開催され、総合せき損センター・泌尿器科の木元康介先生から表題の発表がありました。
近年のSSRI服用にともなう様々な有害事象(重大事件に至るほどの攻撃性・自殺念慮・精子に与える影響)の指摘をはじめ、早漏の治療に対するSSRI(選択的セロトニン再吸収阻害剤)の使用が適応外であることも踏まえると、これらのリスクに対応するためには、処方に至るプロセス(患者とパートナーに対する説明と了解)や、処方後の注意深い問診など、極めて慎重な対応が必要である、という趣旨でした。Antidepressant-associated changes in semen parameters.
Tanrikut C, Schlegel PN.James Buchanan Brady Foundation, Department of Urology, New York-Presbyterian Hospital/Weill Medical College of Cornell University, New York, New York 10021, USA.
We describe 2 cases of patients referred for evaluation of male infertility who had antidepressant medication-associated changes in sperm motility and/or concentration. The physical examination and endocrinologic study findings were unremarkable in each case. Analysis of the initial semen specimens revealed oligospermia, impaired motility, and abnormal morphology in each patient while they were taking serotonin reuptake inhibitors. Repeat semen analyses performed 1 to 2 months after discontinuation of the antidepressants demonstrated marked improvements in sperm concentration and motility. Additional assessment of the potential impact of antidepressant medications on male fertility is warranted.
PMID: 17270655 [PubMed – indexed for MEDLINE]
Antidepressants and Violence: Problems at the Interface of Medicine and Law
David Healy, Andrew Herxheimer, and David B Menkes
PLoS Med. 2006 September; 3(9): e372. Published online 2006 September 12. doi: 10.1371/journal.pmed.0030372.
PMCID: PMC1564177
【PDF形式はこちら】「うつ病」内科で薬処方 使い方誤り攻撃性増す?
2009年3月14日 20時51分 ( 2009年3月14日 20時51分更新 )副作用が少ないと人気の抗うつ薬SSRIを服用し、暴力などの攻撃性が高まった疑いもある症例が4年半で42件報告されていたことが分かった。厚労省では、初期症状の患者らが精神科を敬遠して内科にかかり、使い方を誤って逆に副作用が強く出た可能性もあるとみている。うつ病患者が社会から誤解を持たれないためにも、抜本的な対策が求められそうだ。
副作用少ないSSRI、「攻撃性」疑い42件も
うつ病の初期のころは、精神科へ行くのに抵抗がある人は多い。自覚症状がなく、動悸がするなどの体の異常を訴える場合もある。そして、まず内科にかかることになる。
そこでは、パキシルなどの「SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)」が使われることが多い。効果的な抗うつ薬として一般的な「三環系」と違って副作用がきつくなく、仕事や家事をしてもらいながら治療できるため、使いやすいからだ。
ところが、そのSSRIにも、攻撃性を増したりするような副作用が出る可能性があることが分かった。SSRIは、日本では、シェア5割のパキシルのほか、ルボックス、デプロメール、ジェイゾロフトの計4製品がある。それらの製造販売元の各製薬会社は、医師からの副作用報告を医薬品医療機器総合機構に上げており、それが2008年秋までの4年半に、前述のような副作用も疑われる症例が42件もあったというのだ。
これは、業界紙の医薬経済社が08年9月に同機構に情報公開請求した結果、同12月に公開され、09年3月に入って同紙がその内容を報じたものだ。
それによると、人を実際に傷つけ刑事事件にもなったケースが6件あり、うち1件は妻を殺害したものだった。殺害したのは、認知症にもかかっていた70歳代の男性で、パキシル服用後のことだった。ほかに、妻の頭を金属類で殴って重傷を負わせた45歳の男性もいた。
傷つけるまではいかなくても、その恐れがあったのが13件。「このままでは人を殺してしまう。刑務所に入れてくれ」と望んだ男子高校生やバイクを蹴ったりする人もいた。残る23件は、興奮してイライラするなどしたケースだった。気分が上がってくるときの服用は危険
SSRIは、1999年に日本で承認され、パキシルは2000年から発売された。今では、100万人以上が使うほどSSRIがポピュラーになったが、副作用が少ないというのは間違っていたのか。
この疑問に対し、厚労省医薬食品局の安全対策課長は、こう説明する。
「うつ病の方は、いつも沈んでいるわけではなく、波があって、気分が上がってくるときがあります。そのような状態でSSRIを服用すると、気分を増幅させる危険があるのです。そして、半端ではない興奮状態になったり、怒りっぽくなったり、ときには人を傷つけたりするかもしれません。また、自殺リスクが上がることもありえます」
つまり、精神状態を見て使わないと、意外な副作用が出てくるということだ。
古典的な三環系は、使い方が難しいので、扱いに慣れている精神科の専門医が処方する場合がほとんど。ところが、SSRIは、副作用がきつくないので、内科医でも処方され、十分な注意喚起がないまま、気分が上がってくるときに使われている恐れがあるというのだ。
ただ、うつ病患者は、薬を服用しなくても、気分が上向いているときなどに攻撃的になることがあるとされる。服用しなければ、自殺の危険も強い。従って、他害行為や自殺を防ぐためにも、投薬治療は必要だ。大切なのは、SSRIは、前述のように使い方を誤ると、副作用として「攻撃的反応」を増幅させると注意喚起することのようだ。厚労省は、どのように対応するのか。
これに対し、前出の安全対策課長は、こう説明する。
「確かに、怖くなって薬を飲むのを止めたり、うつ病患者は危ないと思う人が出たりすると、害が大きいと思います。本来なら、精神科の専門医によく聞くのが大切でしょう。しかし、抵抗がある人もいて、呼びかけだけでは難しいと思っています。そこで、内科医などにも人を傷つけるような副作用の可能性があることを注意喚起してもらうよう、何らかの対策を検討しています」抗うつ薬で暴力など42件 厚労省が因果関係調査
2009/03/07 12:31 【共同通信】抗うつ薬の「パキシル」など4種類のSSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害剤)を服用した患者に、他人に暴力をふるうなど攻撃性が高まる症状が表れたとの報告が2004年から昨年秋までに計42件、医薬品医療機器総合機構に寄せられ、厚生労働省は7日までに、因果関係の調査を始めた。
メーカー側に見解を求めるとともに近く専門家の意見も聞き、攻撃性についての注意書きを盛り込む方向で、添付文書の改訂を指示することを検討する。
厚労省によると、報告があったのはパキシル、ルボックス、デプロメール、ジェイゾロフトの4社4製品。42件のうち「人を殺したくなった」など他人を傷つける恐れのある言動をしたり、実際に暴力をふるったりした症例が19件。残る23件も、興奮して落ち着きがなくなるなどの症状が表れたという。
因果関係は不明だが、うつ病を併発した認知症の70代の男性がパキシル服用後に妻を殺害するなど、刑事事件に発展したケースもあった。
SSRIは、脳内の神経伝達物質セロトニンの濃度を調節して神経の活動を高める薬。三環系と呼ばれる従来の抗うつ薬よりも副作用が少なく、うつ病治療に広く使われており、国内でも推定で100万人以上が使用しているとみられる。
厚労省は「うつ病以外の患者にも使われていなかったかなど慎重に調べたい」としている。「抗うつ薬で攻撃性」副作用の疑い42件 厚労省調査
2009年3月7日6時16分 【asahi.com】銃乱射で客ら8人死亡 米中西部の商業モール
2007/12/06 01:45 【共同通信】【ロサンゼルス5日共同】米中西部ネブラスカ州オマハのショッピングモールで5日午後2時(日本時間6日午前5時)ごろ、若い男がライフル銃を乱射した。地元警察当局によると、クリスマスの買い物などに来ていた客ら8人が死亡、重体2人を含む計5人が負傷した。犯人の男は自殺した。 米国では4月のバージニア工科大事件をはじめ銃乱射事件が続発、一般市民が犠牲になる惨事が繰り返されている。 地元テレビによると、犯人は近くに住む20歳で、自宅に今回の犯行をほのめかすメモが残っていた。11月にアルコール所持容疑などで逮捕され、今月19日に裁判所に出廷する予定だったという。 知人とみられる地元女性は地元テレビに、男が最近職場を解雇され、銃を持っているのも見たと語った。別の友人男性は男が抗うつ剤を服用していたと話した。警察当局は詳しい動機を調べている。
全抗うつ剤にリスク記載へ 若者の自殺企図で厚労省
2007/11/06 21:11 【共同通信】厚生労働省は7日までに、国内で販売されているすべての抗うつ剤に、「24歳以下の患者で自殺を企てるなどのリスクが増加するとの報告がある」との内容を使用上の注意として記載するよう、製薬会社に添付文書の改訂を指示した。 米食品医薬品局(FDA)が今年5月、米国内で同様の改訂を指示したのを受けた措置。 ただ抗うつ薬によるメリットも大きく、今回の改訂では、プラス面とマイナス面を考慮した上で投与するよう記載する。 対象となるのは、新しい世代の抗うつ剤であるSSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)やSNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)のほか、古くから使用されている「三環系」「四環系」と呼ばれる種類も含むすべての抗うつ剤。
大人でも自殺衝動を増加か 抗うつ剤、米当局が警告
2005/07/02 01:36 【共同通信】【ワシントン1日共同】米食品医薬品局(FDA)は1日、抗うつ剤が大人の自殺衝動を強める可能性が最近の複数の研究で指摘されたとして、服用する際は症状の悪化や自殺傾向などを慎重に監視するよう求める警告を発表した。 一部の抗うつ剤が子供の自殺傾向を強める恐れは既に明らかになっており、FDAは昨年、薬の添付文書に強い警告を表示するよう指示した。 FDAは今後約1年かけ、米国で広く処方されている抗うつ剤について大人の患者に自殺を誘発する恐れの有無を評価し、製品への警告表示などを検討する。 今回の警告は、その結論が出るまでの当面の措置。特に抗うつ剤を初めて服用する際や、有効成分の量が変わった時の体調、精神状態の変化に注意し、自殺を考える回数が増えたなどの変化があれば医師の診察を受けるよう求めた。
機長刺殺の男に無期懲役 全日空機ハイジャック事件
2005/03/23 03:11 【共同通信】1999年、全日空機を乗っ取り機長を刺殺したとして、殺人とハイジャック防止法違反(ハイジャック致死)などの罪に問われた無職西沢裕司被告(34)に、東京地裁は23日、求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。 判決理由で安井久治裁判長は「わが国犯罪史上類を見ない危険かつ悪質なハイジャック事案で、航空機の安全な航行に対する社会的信頼を損なった」と厳しく指摘した。 ハイジャック致死罪が初めて適用された事件。動機と責任能力が争点となったが、安井裁判長は「抗うつ剤などの影響により、犯行当時、そう状態とうつ状態の混合状態で、心神耗弱の状態にあった」と認定した。 公判中、2回行われた精神鑑定のうち1回は「心神耗弱状態だった」と結論付けていた。
続きを読む
-
生殖期女性および更年期女性における、卵胞ホルモン含有軟膏剤の皮膚に及ぼす影響の検討
2008年11月16日
日本更年期医学会 第23回学術集会
横浜・2008年(平成20年) 11月16日(日) 第2会場 やまゆり一般口演 演題番号58
生殖期女性および更年期女性における、卵胞ホルモン含有軟膏剤の皮膚に及ぼす影響の検討ウィミンズ・ウェルネス銀座クリニック婦人科
関根さおり, 江夏亜希子, 関根美香, 対馬ルリ子【目的】
更年期女性の主訴の1つである皮膚症状(乾燥感,菲薄化,色素沈着など)を改善することは日常生活を楽にするだけでなく,アンチエイジングの観点からも重要である. 今回我々は卵胞ホルモン含有軟膏剤(以下,軟膏剤)が更年期女性の皮膚の状態をどの程度改善するか,またその効果が生殖器女性とどのように違うかにつき比較検討したので報告する.【方法】
生殖器女性(25~40歳)および更年期女性(45~55歳)各20名を対象とした. 各年代において軟膏剤投与群と非投与群を各10名とし,投与期間は4週間連日とした. 投与前,投与開始後2週間,投与終了時で皮膚の状態(皮丘の数,毛穴の数,毛穴の総面積,肌色)を測定した. 血清エストラジオール値・エチニルエストラジオール値の変動測定,使用前後の主観的皮膚変化についての調査も実施した.【成績】
各年代において,軟膏剤は皮膚のきめ細かさ,明度を有意に改善した.更年期女性における変化は数値に表れる以上に,本人の主観的変化や満足度が大きかった.【結論】
皮膚症状を持つ更年期女性だけでなく,アンチエイジング効果を期待する全ての更年期女性において軟膏剤の適切な投与は症状の改善および満足度の上昇に繋がる可能性がある.続きを読む
-
加齢男性性腺機能低下症候群(LOH症候群)患者におけるテストステロン軟膏(グローミン)塗布後の血清テストステロン・レベルと臨床効果
2008年07月30日
Introduction
テストステロン補充療法は、加齢男性性腺機能低下症候群(LOH)患者の様々な症状を緩和するために適用されている。 LOH患者へのテストステロンの投与にはいくつかの経路があり、とりわけ経皮投与は魅力的な方法である。
Aim
本論文の目的は、テストステロン軟膏(「グローミン」大東製薬工業株式会社)適用後の血清総テストステロン(TT)および遊離テストステロン(FT)レベルのプロファイルおよびLOH患者における臨床的な有効性である。
Methods
健常男性ボランティアおよびLOH患者において、3mgのFL適用後の血清TTおよびFTレベルを調べた。次に、50人のLOH患者に陰嚢皮膚へ1日2回3mg(6mg /日)のGLを12週間投与した。その後、GL適用直前のTTおよびFTレベルを、GL処置後の1時間のTTおよびFTレベルと比較した。さらに、前述の50人のLOH患者におけるGLの臨床効果は、12週間のGL治療後に評価された。
J Sex Med. 2008 Jul; 5(7): 1727-1736
続きを読む
-
2008年07月14日
弊社のテストステロン軟膏「グローミン」は、2003年10月から聖マリアンナ医大・泌尿器科の岩本晃明教授(当時)の研究チームで臨床研究が始められ、既にいくつかの学会で発表と論文掲載がされて来ました。
このほど、泌尿器科紀要誌に投稿・掲載された、グローミンの臨床研究に関する論文に対して、代表執筆者の長野赤十字病院・第二泌尿器科部長・天野俊康先生が、泌尿器科紀要誌の稲田賞を受賞される事になりました。7月26日・17時より京都(芝蘭会館別館)で授賞式と講演会がある予定です。
また、インパクトファクター4.7を誇る、J Sex Med. 2007 Dec 18 に掲載された論文は、Pub Medで参照できます。
続きを読む
-
2008年02月12日
お客様各位
いつも弊社製品のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さて、弊社製品のご購入におかれましては、これまで最寄りの製品取扱施設のご案内が十分に出来ておらず、ご不便をおかけ致しております。私どもの力が至らず申し訳ございません。
また、第1類医薬品(弊社製品の場合、「トノス」「グローミン」)に対するインターネット販売をはじめとする全ての通信販売は、既に可決成立した薬事法改正を踏まえ、平成21年6月までに指定される日から、法的根拠をもって禁止されます。
さらには、上記の日より、第1類医薬品は薬剤師による対面販売と、店頭における医薬品情報の提供が義務となります。そのため、薬剤師がいない業態の店舗(薬種商など)では、第1類医薬品の小売販売が出来なくなります。
そのため、弊社製品のご購入にあたり、今後ますますお客様にご不便をおかけすることが懸念されます。
そこで、法の趣旨(医薬品の適正使用に向けた販売方法)と、お客様の利便性(最寄りの薬局での購入)の両立をめざして、このほど流通関係者のお力添えを賜り、「お取り寄せ相談薬局」を始めることに致しました。
これは、弊社にメールでご希望の製品と、購入希望の地域(市区町村名など)を送信戴きますと、通常は弊社が製品取扱施設を検索してご案内致しますが、ご希望の地域に製品取扱施設が無い場合に、弊社製品を取り寄せ対応で小売販売して下さる薬局を検索して、弊社がお客様にメールでご案内し、お客様のご意向を踏まえてお取り寄せの手配を承るものです。
未だ対応できる製品と地域は限られておりますが、お客様のご不便を少しでも解消できれば幸いに存じます。
詳しくは、こちらの弊社HPをご参照下さいませ。今後も変わらぬお引き立てほど謹んでお願い申し上げます。大東製薬工業株式会社
代表取締役社長 福井厚義 拝続きを読む
-
2007年04月17日
平成18年6月8日に国会で可決成立し、同年6月14日に公布された「薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)」の第36条の3(一般用医薬品の区分)について、平成19年3月30日付で関係省令と指定告示が公布され、同年4月1日より適用されました。本法の施行は平成21年6月からとなります。
この告示によりますと、弊社製品の分類は次のようになります(弊社HPに一覧表を設けました)。
【第一類医薬品】
・テストステロンを有効成分として含有する製剤。
「トノス」「グローミン」「ヘヤーグロン」・塩酸ヨヒンビンを有効成分として含有する製剤。
「ガラナポーン」「ガラナピン」【第二類医薬品】
・エストラジオール、エチニルエストラジオールを有効成分として含有する製剤。
「ヒメロス」「バストミン」この法改正により、弊社製品の小売販売は経過措置を経て、平成21年6月までに、次のようになります。
-
- 第一類医薬品は、薬剤師の対面販売のみとなります。すなわち、薬剤師のいない薬店では販売が出来なくなります。
また、ネット販売等の通販が法的根拠をもって禁止されます。
さらに、消費者が説明を求めなくても販売時に注意説明をする事が義務づけられます。
なお、店舗においては消費者の手が届かぬようにカウンターの向う側へ商品陳列することが義務づけられます。 - 第二類医薬品は、薬剤師または登録販売者がいる薬局・薬店での対面販売となります。
すなわち、ネット販売等の通販が法的根拠をもって禁止されます。
また、店頭においては販売時の説明が努力義務とされます。 - 医薬品は店頭で分類毎に分けられた場所へ商品陳列する事になります。
- 製品の外箱にリスク分類の区分を表示することが義務づけられます。ただし、表示方法に関する規定は未だ何も決まっていません。
経過措置は平成23年6月までとされていますが、表示方法が決定次第、規定に準じて順次対応して行く予定です。
- 第一類医薬品は、薬剤師の対面販売のみとなります。すなわち、薬剤師のいない薬店では販売が出来なくなります。
以上に関する弊社へのお問い合わせは、こちらからお願い申し上げます。
続きを読む
-